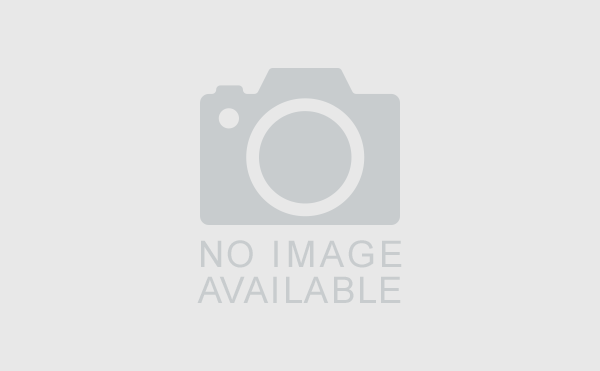相続時精算課税制度における基礎控除
相続に関心がおありの方なら一度は耳にされたことがあると思われる相続時精算課税制度ですが、令和5年度税制改正において暦年課税制度同様に基礎控除が創設されました。
今回は「相続時精算課税制度における基礎控除」について解説します。
- 相続時精算課税制度とは
- 相続時精算課税制度における基礎控除
- 計算例
- まとめ
相続時精算課税制度とは
そもそもの相続時精算課税制度についてざっくり説明をすると「60歳以上の父母または祖父母などから、直系卑属である推定相続人または孫(いずれも18歳以上に限る)への贈与につき、2,500万円までは贈与税が非課税となる」という制度です。
ただし、実際に相続が発生した際には、その時点で残っている相続財産に加えて、相続時精算課税制度を使って行ってきた贈与に係る財産も加算して相続税を計算することとなります。また、加算する財産額は、原則として贈与を行った際の時価によることとなります。
この後ご説明する基礎控除が創設されるまでは、相続時精算課税制度を活用されるケースとして
〇 そもそも相続財産が2,500万円までには至らなさそうであり、早い段階から
子や孫に、贈与税の負担をさせることなく財産を移転していきたい
〇 相続時に加算する財産額が贈与時点での時価に固定されることから、将来値上がりがかなりの確度で見込まれる財産について、早期に贈与をしておきたい
という限定的な場面が多く、本制度の利用状況は低調な推移であったようです。
相続時精算課税制度における基礎控除
そんな中、令和5年度税制改正において「相続時精算課税制度における基礎控除」が創設されました。
従来の暦年課税制度における110万円の基礎控除についてはご存じの方が多いかと思われますが、
同様の基礎控除が相続時精算課税制度にも導入されたというイメージになります。
この相続時精算課税制度における基礎控除は、令和6年1月1日以降に行われる相続時精算課税に係る贈与から適用となります。
詳細をお知りになりたい方は、下記の国税庁のリンクをご覧ください。
参考 相続時精算課税制度のあらまし|国税庁
計算例
① 相続時精算課税制度を用いて、下記の財産について父から子へ贈与を実行
(他に生前における贈与はなかったものとする)
A 令和6年9月1日 1,000万円の預貯金
B 令和7年3月1日 500万円の預貯金
② 令和8年1月10日 父の相続が発生
【相続時に加算される相続時精算課税適用財産】
Aについて 1,000万円-110万円=890万円
Bについて 500万円-110万円=390万円
合計 890万円+390万円=1,280万円
まとめ
相続時精算課税制度における基礎控除が創設されたことにより、同制度が改めて注目を浴びています。
基礎控除創設後初となる令和6年分の贈与税の申告においては、相続時精算課税制度を選択された方が
かなりの数増えたようです。とはいえ、個々の状況により相続時精算課税制度の選択が必ずしも
最適解になるとは限らないため、適用を検討される方は専門家の判断を仰ぐことが重要です。
税理士法人フォースでは、生前贈与のご相談や相続税額のシミュレーションなどにも幅広く
対応させていただいております。
ご関心のおあるになる方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。